悲喜交流
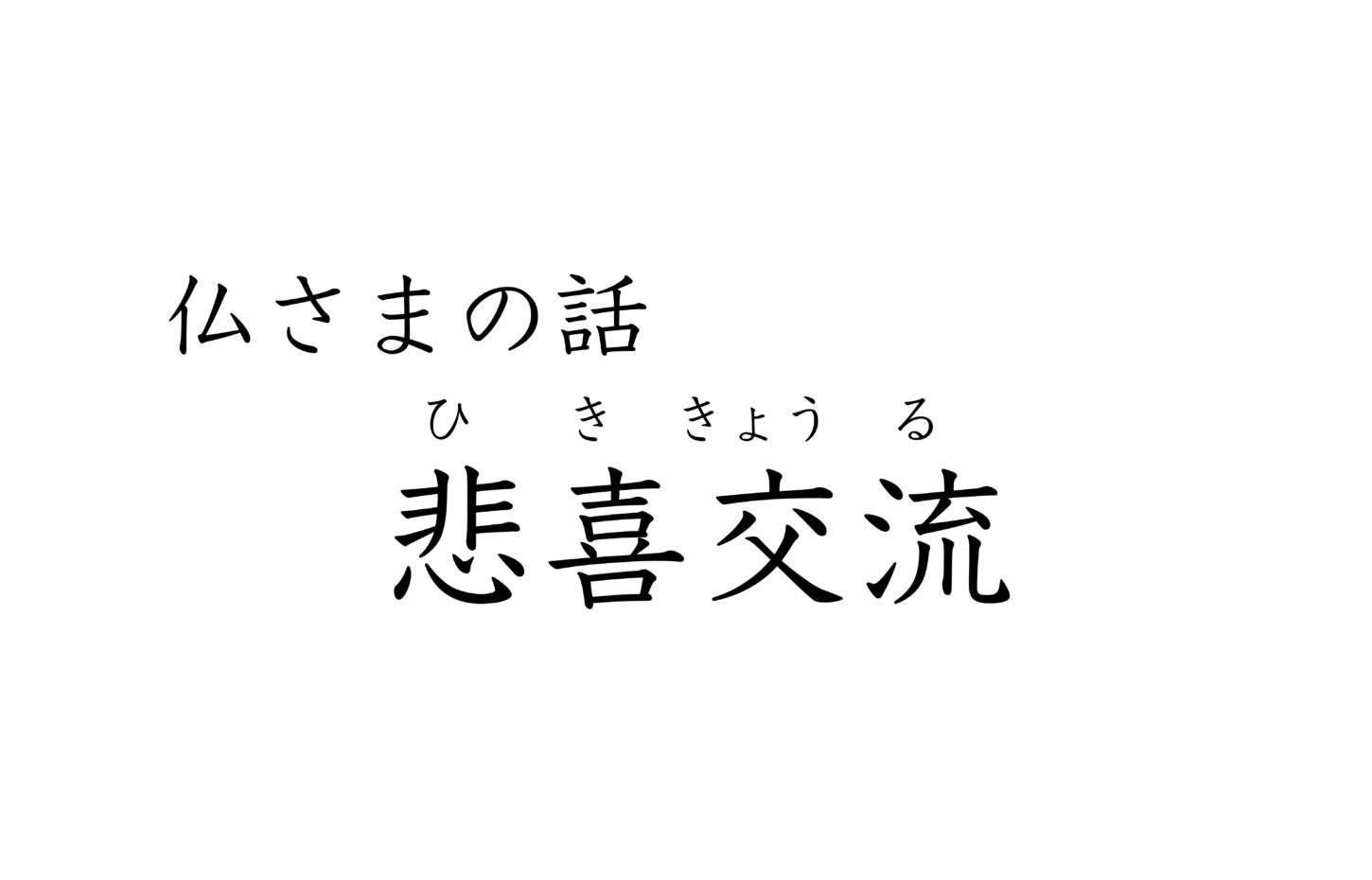
「たはむれに母を背負ひて そのあまり軽きに泣きて 三歩あゆまず」
この歌は、詩集「一握(いちあく)の砂」におさめられたの歌です。啄木は、その26年と53日の人生を文学に捧げ、文学とともに生きました。
明治19年に現在の盛岡市に生まれ、14歳で与謝野鉄幹・与謝野晶子に傾倒。16歳で学校を中退し文学の道を志して上京します。19歳の時には節子と結婚をして子どもをさずかりながらも住む場所を盛岡、函館、札幌、小樽、東京と変え、いくつもの職場を転々としながら文学を続けます。文学だけでは食べていけず、定職にもつかないものだから自ずと生活は困窮し、家族とも同居や別居を繰り返し、不安定な生活を送ります。時には自死を考えたり、自虐的な生活に陥ったりするときもあったようです。それでも家族や仲間たちに支えられながら、その折々の心境を飾ることなく歌にしたためてゆき、26歳で病のため亡くなりました。
あるとき、啄木が楽しく母と語らっていました。昔話でもしていたのかもしれません。遊びの延長で母を背負ってみることになりました。「いくら年を重ねたといえども、まだまだ重たいに違いない、もしかしたら背負えないかもしれないな」と、高をくくっていた啄木。しかし、背負ってみると軽々と背負えてしまいました。そのあまりの軽さに啄木は驚愕します。背中の母からは、幼い頃に自分を育ててくれた、あの力強さ、たくましさはまったく感じ取ることができません。啄木の目から涙がポロポロ溢れてきます。そして我が身を顧みて「文学にのめり込んで、自分勝手に生きてきた私を、母はいつも心配して支えてくれた。母をこんなに軽くしてしまったのは自分かもしれない」と悔やみ、3歩すら歩けぬほど、軽くなった母が重たかったというのです。
浄土真宗(じょうどしんしゅう)を開かれた親鸞聖人(しんらんしょうにん)は、阿弥陀仏(あみだぶつ)という仏さまに出会われたときに、「阿弥陀さまが積まれた計り知れないご苦労は、どこまでも煩悩を起こし、迷いを重ねて生きている私のためのご苦労であった」と深く我が身を悔やみ、悲しまれていらっしゃいますが、その心情のさらに深いところを存覚上人(ぞんかくしょうにん)という方が読み取られてこのようにおっしゃっています。
「悲痛すといえども、また喜ぶ所あり。寔(まこと)にこれ悲喜交流(ひききょうる)というべし」(六要鈔)
(この悲しみの中には喜ぶところがあるのだ。それは、こんな私のためにここまでご苦労くださる仏がいらっしゃったという心である。それゆえ悲喜交わり流れる心である)
改めて石川啄木のこの歌を味わいますと、母をこんな姿にしてしまうほどの親不孝の私であったという悲しみの歌であると同時に、こんな姿になりながらも自分のことを心配して支えてくれる母がおったかという喜びの歌にも思えて、まさにの心情に思えるのです。
我が身にかかり果てる大きなお心にであうときに、人は悲喜交流の心情を抱くものなのかもしれません。
称名

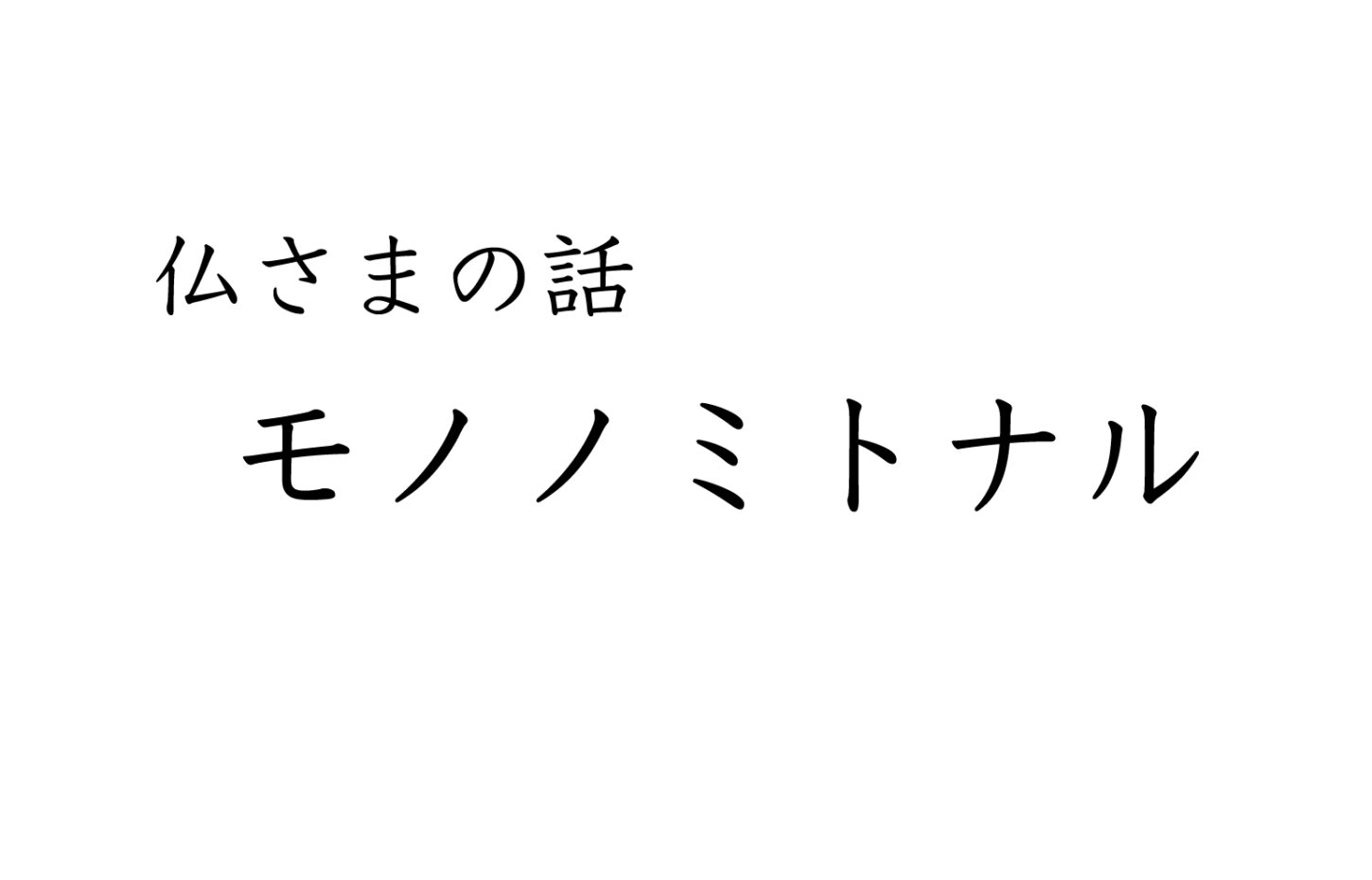
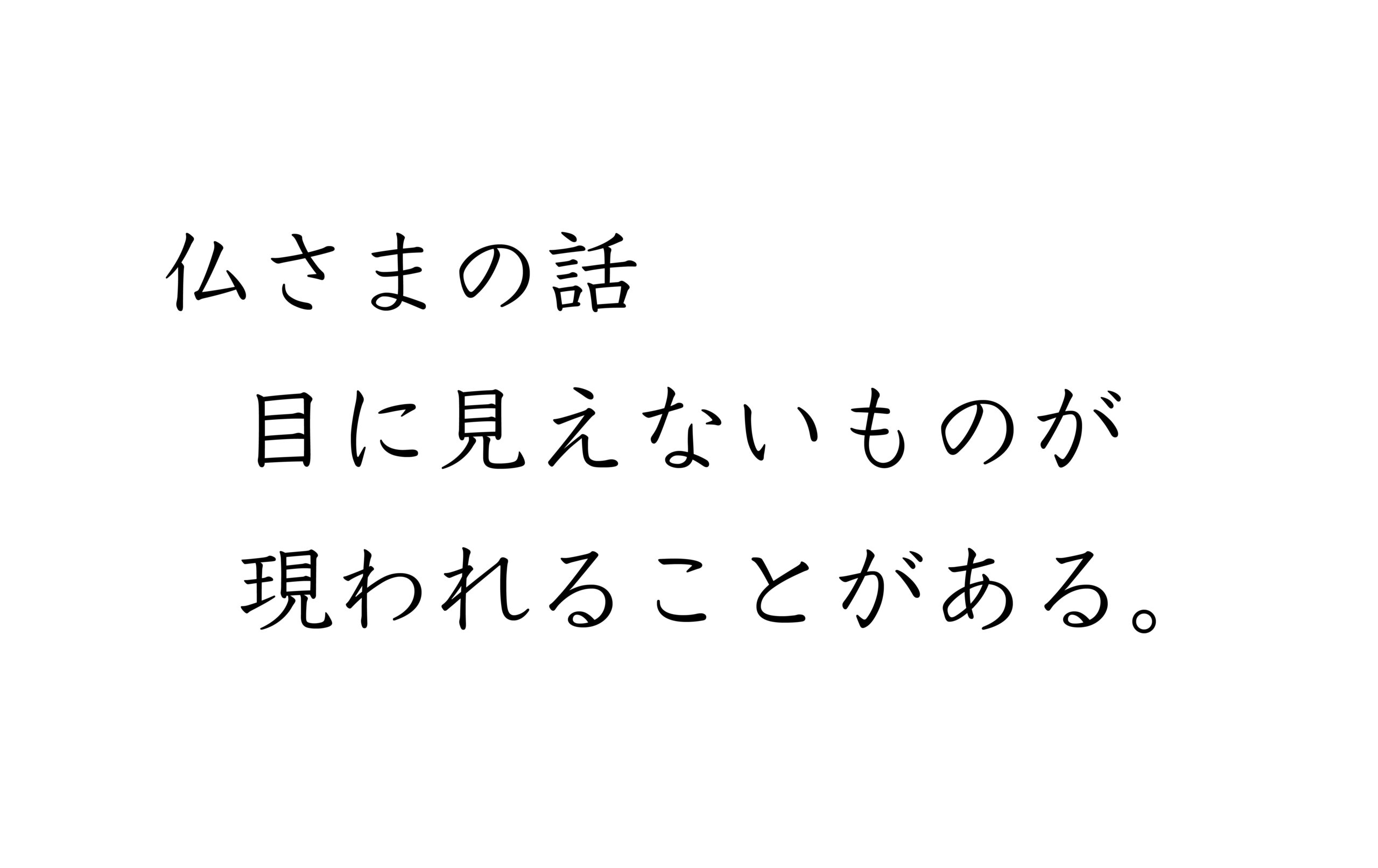
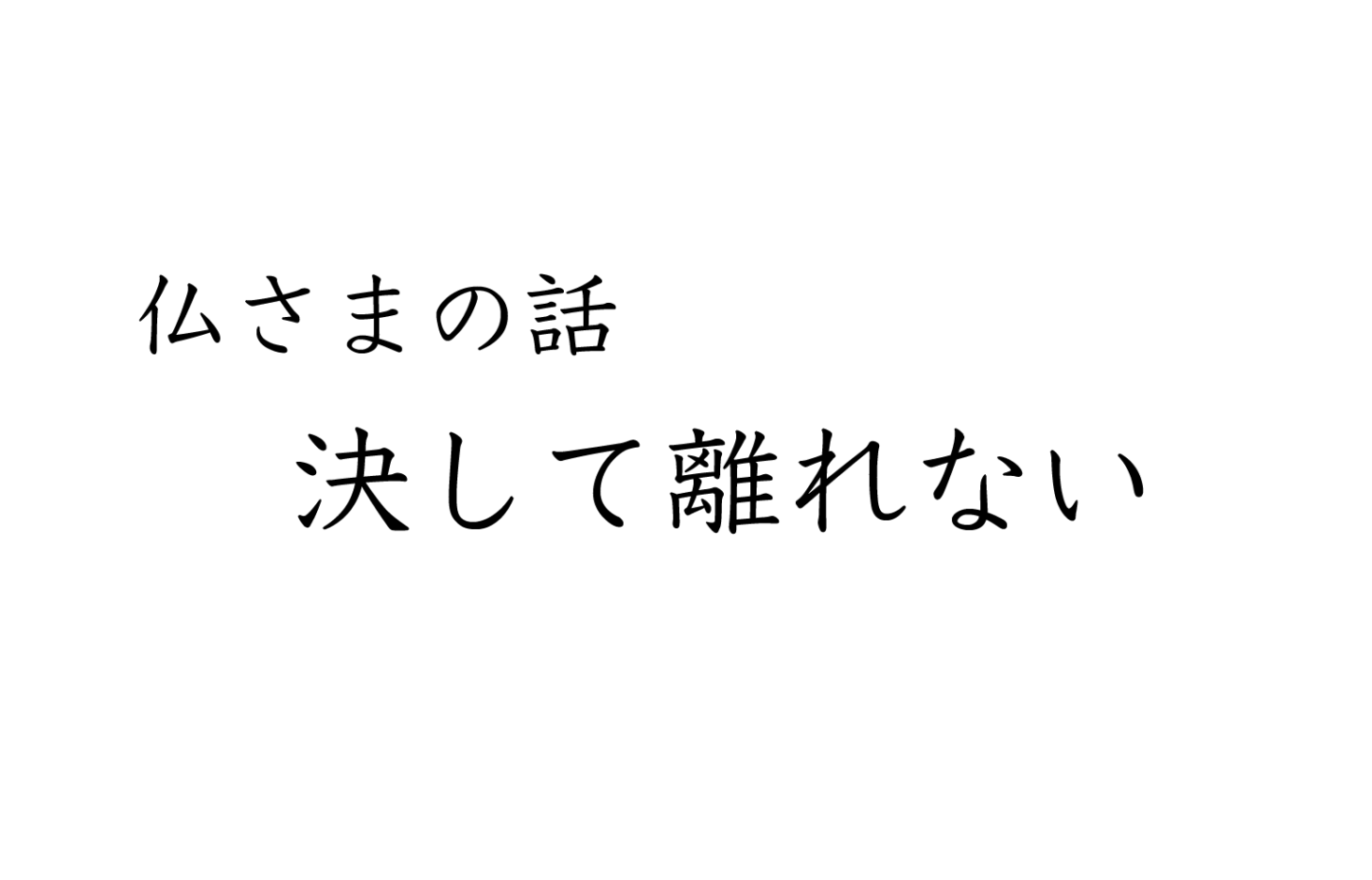
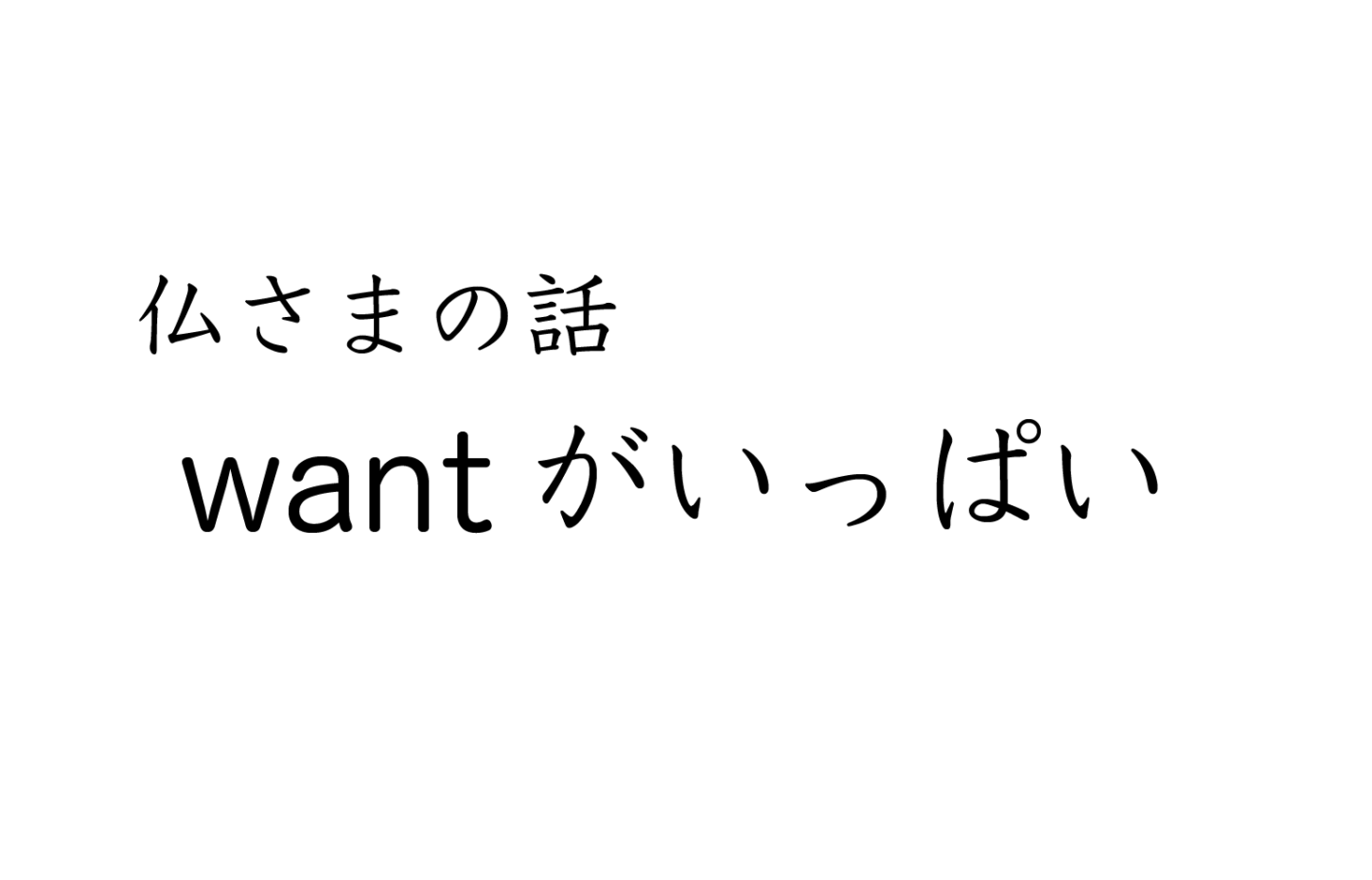

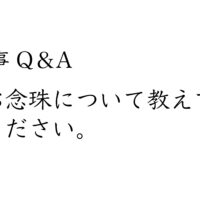
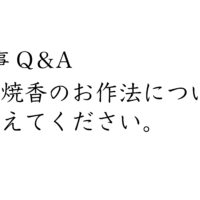

この記事へのコメントはありません。