名前の仏さま

いはんやわが弥陀(みだ)は名をもって物を接(せっ)したまふ。
ここをもつて耳に聞き口に誦(じゅ)するに、 無辺(むへん)の聖徳(しょうとく)、 識心(しきしん)に 攬入(らんにゅう)す。〈元照律師〉
浄土真宗(じょうどしんしゅう)のご本尊を阿弥陀仏(あみだぶつ)といいます。阿弥陀仏は、すべてのものをどんなことがあっても見捨てることなく、浄土(じょうど)という素晴らしい世界に生まれさせ、仏にするとお誓いくださり、私たちのところに“南無阿弥陀仏(なもあみだぶつ)”という言葉となって届き、どこまでもはたらき続けてくださいます。
ある法事で、ご年配の方からこのようなことを言われました「住職さんはいつも阿弥陀さまの話ばかりするね。でもね、私は目に見えないものは信じることができないです。阿弥陀さまが私の目の前にドーンとあらわれてね、あなたを救うよと包み込むのであれば、信じることはできるんだけどもね」と。お話を聞きながら、その気持ちよくわかるなと思いました。しかし、私たちの目はそんなに確かなものでしょうか?
私は遠くも近くもよく見える視力1.5の眼をもっているのですが、この頃、案外この目はあてにならないなと思うことが度々あります。先日、いつも通っている道の一区画が更地になっていました。すると更地になる前に何があったかを思い出そうにも思い出せないのです。いつも見ていたはずなのに、見えていなかったのでしょう。また、相田みつをさんの詩「花を支える枝、枝を支える幹、幹を支える根、根はみえねんだなあ」を読んだ時に、毎年行く花見の光景を思い出しました。そこには私を含めて何千人という花見客が首を上に向けて「今年の桜(の花)も素晴らしいね」と言いながら歩いています。誰一人として「こんな桜の花を咲かせる木の根や幹や枝って素晴らしいね」と下を向きながら歩いている人はいません。枝や幹や根っこは目の前にあるのに、その素晴らしさはなかなか見えません。中でも一番この目はあてにならないなと思った出来事は父親の遺品整理でした。私が鹿児島に帰ってきてから、父とは8年ほど一つ屋根の下で過ごし、その姿はよく見ていたはずでした。しかし、父が亡くなってから出てきた日記・闘病記録・大事にしていたもの・昔の写真などから見えてきた姿は、私が見ていた父とは大きく違うものでした。目に見えるものしか信じることができないとの考えをお持ちの方はとても多いと思いますが、この目はなかなかあてになりません。ですから、仏さまが見えない原因は、仏さまにあるのではなく、私たちの側にあるのかもしれません。
中国の伝説に鸞(らん)という鳥がいます。姿は鶏に似ており、赤みを帯びた羽から煌びやかな五色の光を放ち、鳴けば五つの音色の美しい音色を奏でる、誰もがうっとりする美しい鳥として描かれます。その鸞は子育てに特徴があります。鸞のヒナは真っ黒の見窄らしい姿をしており、美しすぎる親鳥のことを自分の親と認識できません。そのため餌を与えられても食べようとせず、寄り添われても拒んでしまいます。そのヒナをなんとかして立派に育て上げたい親鳥は、ヒナたちが待つ巣に戻る前に一つの工夫をします。それは、泥沼に飛び込むということです。泥水に飛び込んで、わざと煌びやかで美しい身体を真っ黒く汚し、ヒナが親と認識できる姿となってから餌をあたえ、寄り添い、育てていくのだといいます。
親を親と認識できないヒナのところに、美しい鸞が泥をかぶって現れたように、阿弥陀仏の姿を目に見ることができない私たちのところに南無阿弥陀仏の言葉となって顕れ、この命を決して見捨てぬ存在がいることを、今、溢れんばかりに願われていることを知らせてくださいます。そのところを元照律師は「阿弥陀仏は南無阿弥陀仏という名でもって私たちをお救いくださる。そうであるから、その名を耳に聞き、口に称えるところに限りない功徳が満ち満ちるのだ」とお示しくださっています。
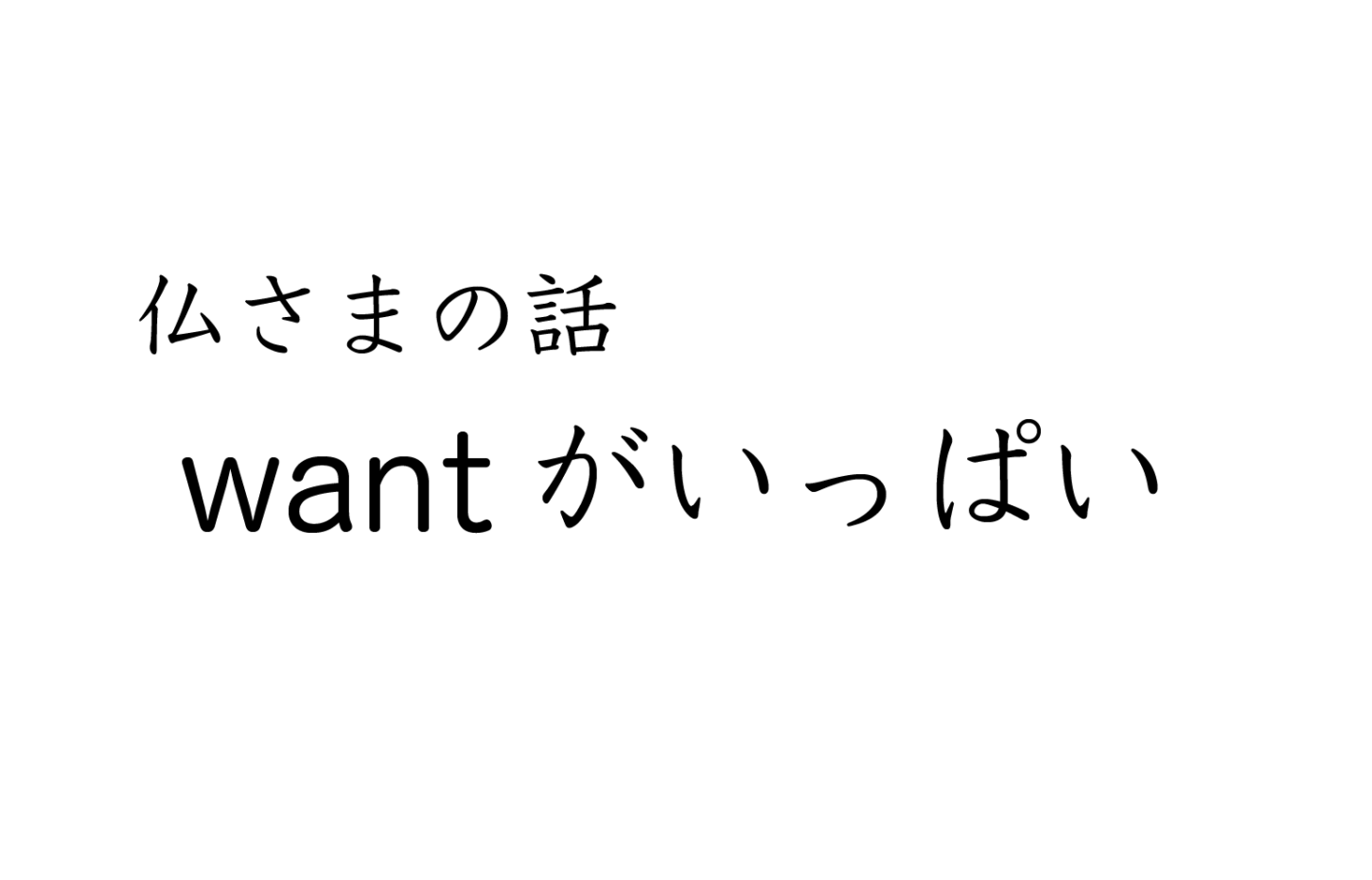
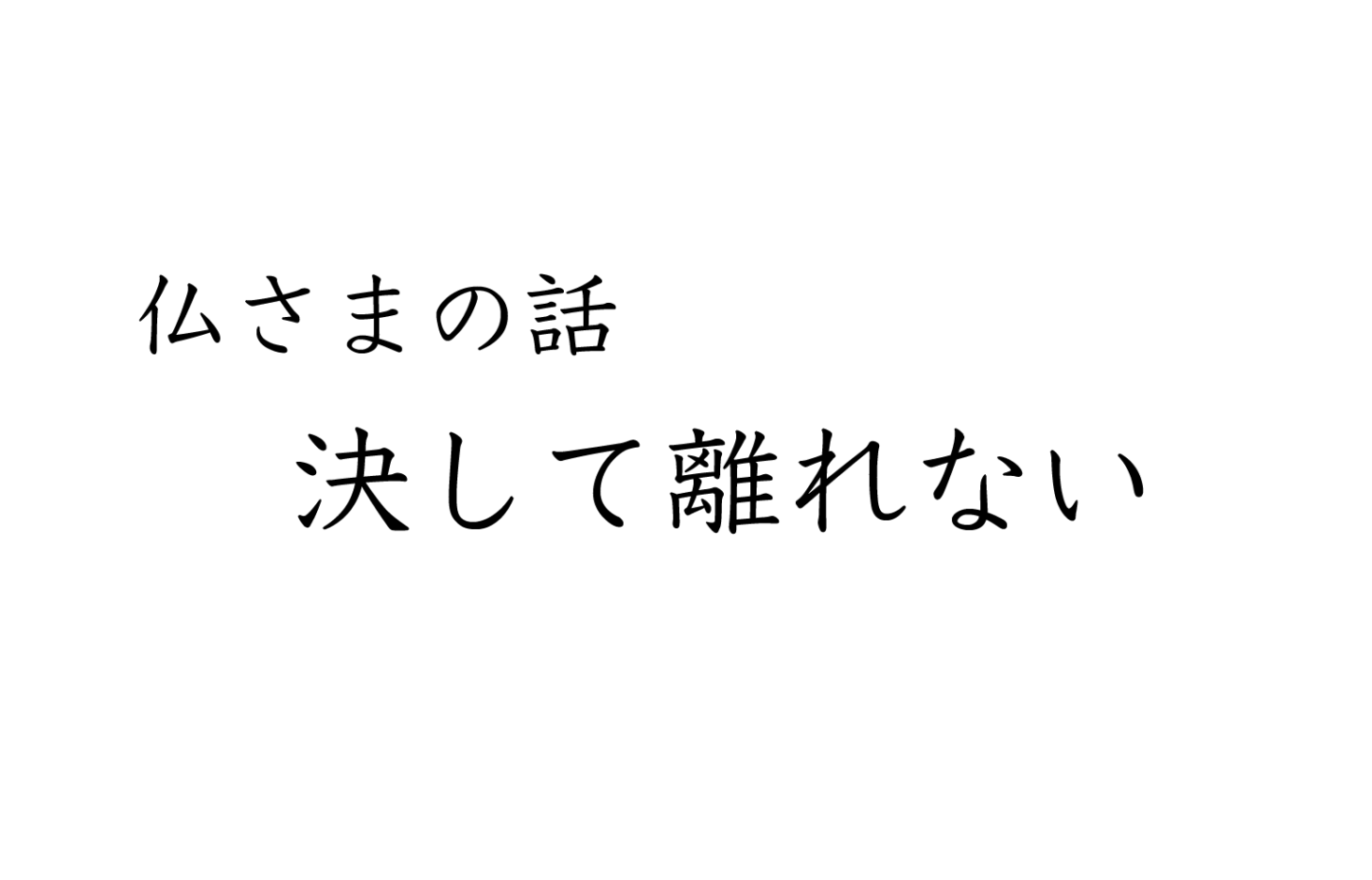
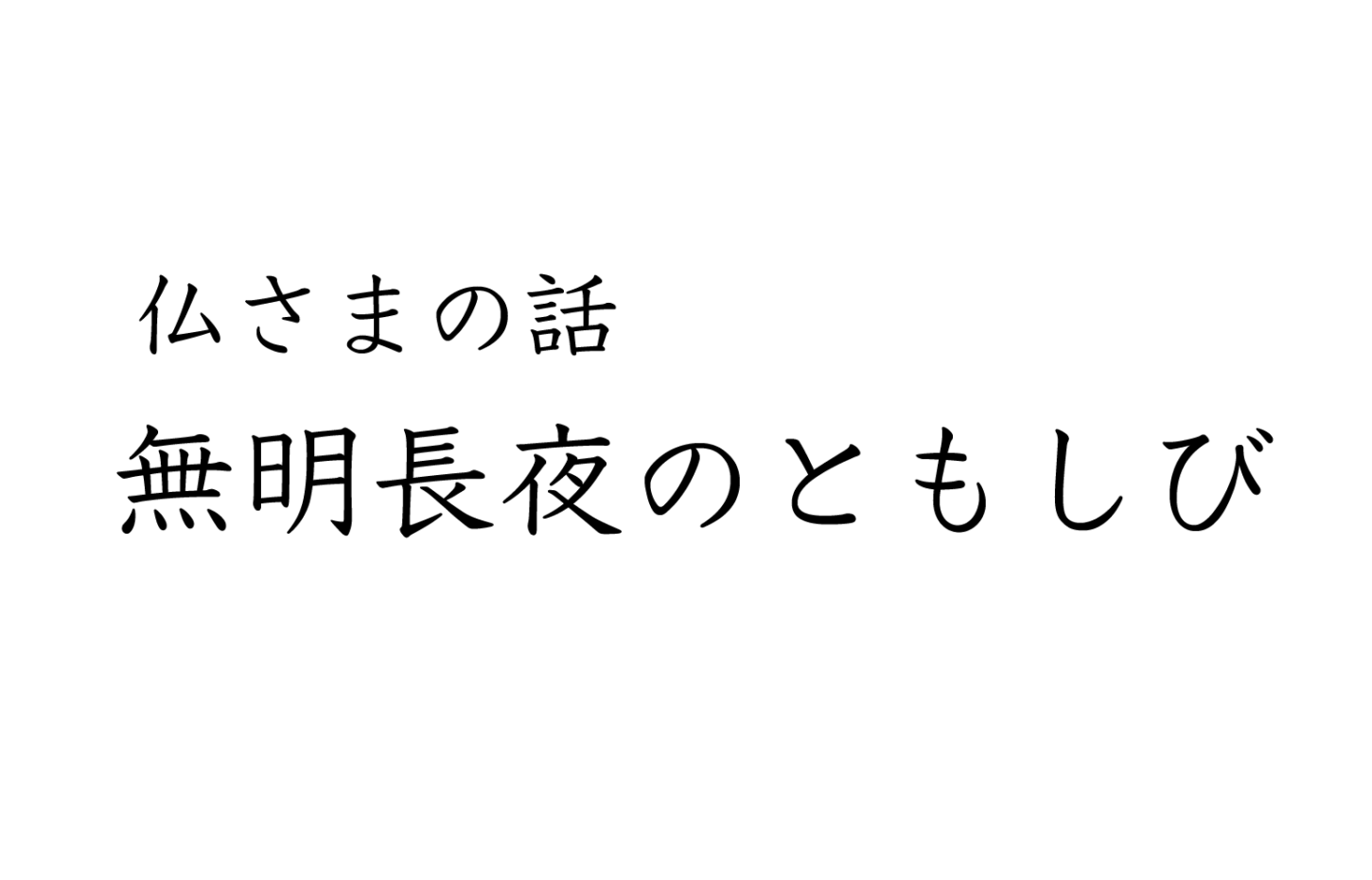


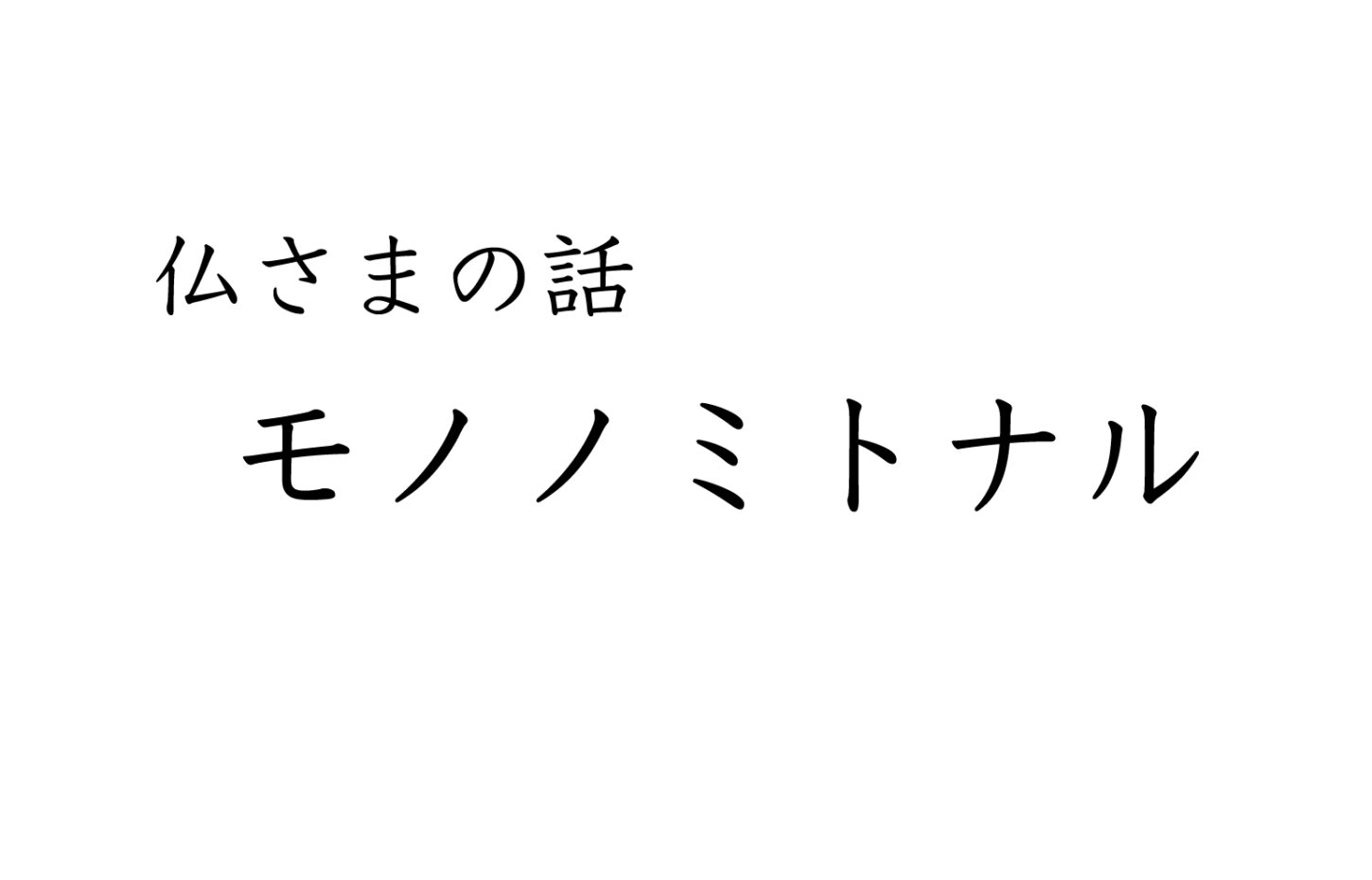
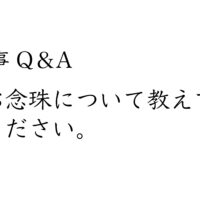
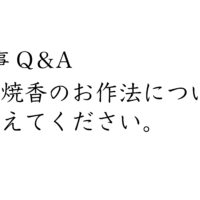

この記事へのコメントはありません。