更新中! 新疆ウイグル自治区カシュガルの旅

6月1日 暗闇に向かう旅

鹿児島を飛びたったのは、5月31日の肌寒い朝だった。
羽田、北京そしてウルムチを経由して6月1日の朝。中央アジア、キルギスに到着した。
ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、中国に囲まれたこの国は、日本よりも少し早く夏を迎えようとしていた。
到着ゲートをくぐった私に、早速2〜3人の客引きが声をかけてきた。
「タクシー?」
「乗らない。バスを使うから大丈夫」
「街までは遠いよ」
「大丈夫だよ。ありがとう。」
「そうか。わかった」
と彼らは風が通り抜けるようにあっさりと引き下がった。入国してすぐの客引きで嫌な気分になる国は、おおかた現地人とのやり取りで苦労することが多い。その一瞬の軽さに、この国の人らの透明さを見た気がした。
空港内の売店で2000円支払いSIMカードを購入した。このカードを手持ちのスマホのものと差し替えるだけで、いつものスマホが特別な通信料を払うことなくこの国で使えるようになる。昔は海外で携帯電話を使うなど、夢のような話だった。あの頃は、日本に連絡を取りたいときはインターネットカフェと呼ばれる型落ちしたパソコンがずらり並んだ商店に行って、日本語がインストールされたものを探し、メールを送信したものだった。日本語が使えるパソコンが見つからないときは、ローマ字入力でkonnichiha gennkidesuka?(こんにちは元気ですか)などと打って送ることになり、それを受け取った友人は「パソコンがハッキングされた」と慌てたことがあった。
今やスマホを持っていれば、地図機能、写真や動画をとる機能、翻訳や通訳の機能、現地通貨を日本円に換算する機能、評判のいい宿や食堂を検索する機能などすべてこれ一台でできる。旅をする上でなくてはならないものであるが、これによって旅がつまらないものになってしまっているのも否めなかった。
スマホのない時代の一人旅は、常に先の見えない真っ暗闇に飛び込んでいく感覚だった。現地の人から教えてもらう情報と、紙媒体の地図、そして安宿に備え付けてあるボロボロの宿帳をたよりにした。その宿帳には、「〇〇レストランが美味しい」「〇〇という観光地には◯番バス停から乗ったらいい」「〇〇地域は危険だから行かない方がいい」といった情報がたくさん書かれていた。それは宿に泊まった先輩旅人が、あとからやってくる人のために残してくれていた情報であった。その情報をたよりに旅をしたものは、また次にやってくる旅人たちのために、知り得た情報を書き残した。宿帳を通して、どこの誰ともしらない人らと情報交換、優しさのやり取りを楽しむこともできた。
予定調和のない旅は、素晴らしい出会いがあるとそれは何ものにも代えられない大きな感動に包まれたし、また別れの際にはもう2度と会えぬと涙を流し手を振り続けた。一つ一つのハローグッバイが旅の思い出に皺を刻み、一層忘れられないものになっている。私は未だに、そんな真っ暗闇に飛び込んでいくような旅に憧れている。このキルギスを選んだのも、ネットにもガイドブックにも情報はほとんどなく、そんな憧れの旅ができそうだったからである。
SIMカードを購入した私は、ATMで現地通貨を下ろしてから空港の外へ出た。空はどんより曇り。しかしカラッと暑い。空港の外れにある通り沿いに空っぽのバスが2台並んで止まっていた。どうやらこれが都市部へ向かうバスのようだった。先頭のバスを覗くと運転手がハンドルにもたれ掛かりながら声をかけてきた。
「日本人?」
「ああ」
「キルギスは初めて?」
「うん」
「今着いたところか?」
「うん」
「ようこそキルギスへ!」
彼はニコッと笑い、大きな声でそう言った。その一言が嬉しく、担いだ荷物が軽くなった気がした。都市部までは30キロほどあるという。運転手のすぐ後ろの席に座り「中心部に着いたら降ろしてほしい」と頼んだ。バスが走り出し、遠くにポツポツ浮かぶ動かない雲を眺めているうちに寝てしまっていた。運転手がバックミラー越しに「この辺が中心部だ」と声をかけてくれた。降ろされたのは4車線と4車線が交じり合う、それなりに車の通りがある交差点だった。
バスのドアは無機質な音を立てて閉まり、走り去っていった。都市部だと言うから降りてみたけれども、高いビルや立派な建物は見当たらず、のっぺりと面白みに欠ける景色が続いている。遙か遠くに溶けきらぬ雪に覆われた山々がうっすら見えていた。私は木陰に座った。
「さて、ここからどうやって新疆ウイグル自治区カシュガルへ行こうか」
新疆ウイグル自治区のカシュガルは、広大な中国の中でも最も内陸に位置する。東シナ海沿いに都市が集中しているのに対して、内陸はぽっかりと空いていて「ここに何があるんだろうか?」と冒険心を掻き立てられる。また、この地域は、中国によって強制的な中国化が進められており、その試みに反対するウイグル人は、強制収容所に送られて再教育をされるらしく、それが国際的な人権問題となっていることも、実際に肌で感じてみたいと興味を引いた。
ただ、日本から新疆ウイグル自治区へ行くルートとして一般的なものは、北京などから中国に入り、飛行機の国内線や長距離列車を使うルートであって、キルギスには来ない。
私も当初、一般的なルートで行こうと思ったのだが、このルートを通ってウイグルを旅した人らのブログを読むと「ウイグルは平和で見どころいっぱい。とっても素敵な観光地♪ルンルン」という平和的な感想がやけに多く、問題多きウイグルなのにどうしてこんな感想を抱くのだろうと不思議に思っていた。ウイグル問題を取り上げた本や記事をいくつか読むと、『ウイグルの問題は、中国政府がうまく包み隠しており、表面には見えずらい』と書いてあった。中国内部を通ってウイグルに向かうルートは中国政府が包み隠したベールの中を旅することになり、問題が見えずらいのかもしれないと、そんな仮説を立てた。そして別のルートで入国する方法はないものかと探し始めた時に、キルギスから行くことができるという情報を得た。しかもこのルートは、国を跨いで物を運ぶトラック運転手と出稼ぎに行くウイグル人労働者が使うものらしく、これならウイグル人たちと密に旅ができるかもしれないと興味が湧いたのだった。
ただ、ネットの情報は乏しかった。陸路で行く上で一番気になるのは国境である。キルギスのビシュケクと新疆ウイグル自治区のカシュガルを結ぶ国境は、トルガルト峠と言われる標高3500メートルに位置する。この国境について、ネットを検索しても、地球の歩き方やロンリープラネットといったガイドブックを読んでもほとんど情報は得られなかった。そこで、在中国日本大使館、在日本中国大使館、中国ビザを発行する機関、中国とキルギスと旅行会社などにメールを送って返事を待つことにした。返事はいくつか返ってきた。中でも一番丁寧に長文で返事をしてくれたのは在中国日本大使館だった。そのメールには、「トルガルト峠は現在通過は可能である」と書かれており、加えてウイグル自治区の危険度を表した外務省のURL、ビザに関すること、国境の開所時間、国境へ持ち込みが禁止されているものなどを親切に書いてくださっていた。旅行会社からは2社返信があった。いずれも「自力での国境越えは無理だ。俺たちに任せれば、なんとしてでも国境を越えさせてやる。金額は8万だ。安いだろう。俺たちは無敵の旅行会社だぜ!」という趣旨のメールだった。「片道8万なんて無理払えない」とすぐさま返信し、選択肢から除いた。もう行ってみるしかないと結論づけ、先ほどキルギスに到着した。
「さて、ここからどうやってカシュガルに向かおう」
暗闇の前に立っている気分だ。
6月1日 旅がまだ始まらない

木陰に腰を下ろし、行き交う人々をぼんやりと眺めていた。家を出てから30時間もかけてここまでやってきたが、それでもまだ旅が始まったという高揚感はなかった。恐らくそれは、遥か遠くにうっすら見える山脈を除いては、どこを見渡しても“日本の延長線”のように感じられたからだ。
キルギス人の顔立ちは驚くほど日本人に近い。歩く人の身なり、街を走る車、建物、道路も、どれも“異国のざらつき”を欠いている。途上国などで見かける路上脇で寝ている人もおらず、歩く人の足取りには確かな目的が見えるのも日本と似ていた。すべてが見慣れた光景だった。それは安心感を与えてくれるのだけれども、非常につまらなく感じた。
時計を見ると、午後1時を過ぎていた。気分を変えようと、ふと目に入った大衆食堂へ入る。地元の人らでほとんど席が埋まっており、古いクーラーがカタカタと音を立てて生ぬるい風を送っていた。ヒジャブ姿の店員に案内された奥の席に座り、「キルギスに着いたばかりだ」と伝えると、彼女はにっこり笑い、2つの料理を運んできた。
一皿目は、焼きうどんのような麺料理。
二皿目は、どう見ても小籠包。
ラグマンとマンティというらしい。この地域の伝統料理だという。どちらもとても美味しい。
ラグマンはシンプルで正直な味付け。普段料理をしない男子学生が肉や野菜を炒め、適当に醤油やソースをドボドボいれて、たまたま完成した奇跡の一皿のような味付け。
もう一つの小籠包は一つの皿に5つ乗っており、スプーンで抱え、かぶりつくと中から容赦ない熱さの肉汁が滴り落ち、口の外まで火傷をした。少し皮を破って中の具材にフーフーと息を吹きかけてから食べた。
そういえば、こういった小籠包のような料理は、コーカサス地方のジョージアでも伝統的な料理として食べられていた。それはヒンカリと呼ばれ、中身は肉肉しく、皮は分厚く食べ応えがあった。慣れ親しんだ小籠包がジョージアワインのお供に出され、当然のように食べられ出るのを見て不思議な気持ちになったものだった。
中国・キルギス・ジョージアに同じような料理がある。中国・キルギス・ジョージアかと頭に浮かべて「あ、シルクロードか」と声が漏れた。
食堂を出て、カシュガルへの行き方を尋ね歩いた。私が話しかけると彼らは皆、少し身構え、少し距離を取りつつも、親身になって考えてくれた。時には周り人に相談したりもして、なんとか答えを持ってきてくれた。しかしその答えは、
「バスはある」
「バスはない」
「西にバスターミナルから出ている」
「西のバスターミナルは閉鎖されてる」
「東のバスターミナルから出ている」
「北バスターミナルから出ている」
つぎつぎと矛盾する答えで、まるで街全体に遊ばれているようだった。
これでは埒が開かず、日本人宿がこの辺りないものかと調べたら、一つ名前が出てきた。「桜ゲストハウス」ここの日本人のオーナーに最後の望みを託すことにした。
6月1日 朝顔の影の下で

午後4時、さくらゲストハウスの門をくぐった瞬間、涼しい風を感じた。植物に囲まれた中庭には、東屋のような休憩所が三つ並んでおり、旅人は吸い寄せられるようにそこへ上がり寛いでいた。どこか静かな避暑地のような空気が漂っていた。
ここは日本人の旦那さんと、日本語が堪能なキルギス人の奥さん、その娘さん、そして数人のお手伝いさんで切り盛りされている。大部屋のドミトリーといくつかの個室がある。
ちょうど私が到着した時、宿の主人が椅子の上に立ち、東屋の屋根から長い蔓のようなものを這わせていた。紫や赤の花がちらりと見えたので「朝顔ですか?」と尋ねると彼は穏やかな笑みを浮かべた。
「日本から苗を一つ持ってきただけなんですが、こんなに増えちゃってね」
吊り下がった朝顔の蔓や葉が気持ちの良い日陰を作っていた。主人自身、その植物たちに溶け込んでしまいそうな、優しい雰囲気の物静かな方だった。
その時、横から妙に張りのある日本語が飛び込んできた。
「今キルギスのゲストハウスに着きました!これからここに◯泊して・・・」
金髪の日本人女性がスマホを自分に向けて動画を撮影している。
近頃、こうして旅の最中ずっとカメラを構え、撮った動画をSNSに上げて旅費を稼いでいる人によく出会う。絶景を前にしても、街を歩く時も、食事の最中でさえもレンズを離さない。そんな姿を見るたびに疑問が浮かぶ。
「旅に出る時くらいは、世間との繋がりを断ち切り、自由になりたくないのだろうか?」
「旅の情景は、カメラではなく、心にしまい込み自分だけの宝物にしたくはないのだろうか?」
チェックインカウンターで、ひとまずドミトリーを1泊確保する。ついでに奥さんにカシュガル行きのバスを尋ねると、手を止め、東屋に座るヨーロピアンの2人を指差した。
「あの女の子たち、今朝カシュガルからバスで着いたばかりよ。聞いてみたら?」
声をかけると、2人は同時にこちらを見た。その顔に正気はなく、明らかに疲れ果てている様子だった。彼女らは、カシュガル行のバスは北バスターミナルから出ていることを教えてくれた。その後、そのバスがいかに過酷なものであったかを渋い顔で語り、「やめた方がいいわ」を繰り返した。
さっき吊るされたばかりの朝顔の花の影が、ちょうど彼女の目や口元でチカチカしていた。
6月1日 不機嫌な窓口係
北バスターミナルは宿からタクシーで15分ほどのところにあった。鉄製の青色の門から小さい乗合バスが呼吸をするように出たり入ったりしていた。
建物に入ると、そこは病室の冷たい待合室みたいで、匂いまでそれに似ている気がした。白と青の制服を着た女性が2人いて、彼女らのカンカンというヒールの音が響いていた。私以外誰もいなかった。窓口で対応してくれた女性は、鼻の横にホクロがあり、席に座ると大きくため息をついた。明らかに虫のいどころが悪いようだった。
彼女と私の間は、防犯用の厚いガラスで仕切られており、お金のやり取りをする隙間だけが開いていた。そのため、彼女が何か言っても聞き取ることができず、私が何か言っても彼女は聞き取ってはくれなかった。私はわずかなその隙間に、話すときは口先を入れ、聞くときには耳を入れた。ますます彼女はさらに不機嫌になり、大声で罵声を吐きながら、とうとう私の方に出てきた。私は再度、カシュガルへのバスはあるかと聞くと、窓の外を指差した。そこには、塗装が剥がれた古いバスと、そのバスに乗るのであろう人々が集まっていた。彼らは他のキルギス人とは明らかに違い、顔の骨格が幾分ゴツゴツして、素朴で、少し赤らんだほっぺたをしていた。身なりも周囲のキルギス人と比べて見窄らしく、みな大きな荷物を持っていた。それがカシュガルへのバスだった。
私は目的のバスを見つけて浮かれ、「何時に出発だ」「値段はいくらだ」「到着は何時だ」と矢継ぎ早にたずねるが、ろくにそれを聞きもせず、「このバスは予約でいっぱいよ。次のバスは4日後」と口元に意地悪な笑顔を浮かべて言い放った。
他の係の人にも聞いてみたが答えは同じだった。この街で4日間過ごすのは非常に退屈だと思ったけれども、仕様がない。とりあえず、次のバスの情報を聞き、宿に戻ることにした。
・このバスターミナルから日曜日と水曜日。次のバスは6月4日水曜日。
・出発は16時。
・事前予約はできない。
・当日は昼には来た方がいい。
・料金 失念
それからの4日間は、昼間は観光し、カフェに行き、日が暮れると酒を飲んだ。4日もいれば、何番のバスに乗ったら都市部にいけるかとか、街中に止めてあるシェアキックボードはどうやって使ったらいいのかとかもわかるようになった。特にシェアキックボードはどこへ行くにも重宝し、それに乗って生ぬるい街をかけぬけると、もう自分の街みたいな気がした。
記事が出来次第 更新していきます🙏






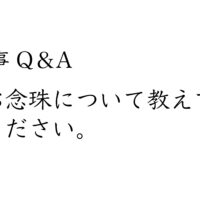
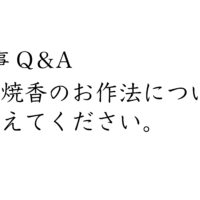

この記事へのコメントはありません。