お墓を管理するのが難しくなってきています。今後どのようにしたら良いですか?

◆浄土真宗のお墓の意味
2006年、秋川雅史さんの「千の風になって」が大ヒットしました。ここには「私のお墓の前で泣かないでください そこに私はいません 眠ってなんかいません 千の風になって 千の風になって あの大きな空を吹きわたっています」とあり、亡くなられた方はお墓の下におらずに風になっているという死生観が書かれています。
浄土真宗で命終えられた方をどのようにいただくかといえば、亡くなられた方はお墓の下にいらっしゃるのではなく、千の風になるのでもなく、南無阿弥陀仏と称えるお念仏の響きのなかに身を置いて、私たちといつもご一緒くださるといただきます。そのため浄土真宗のお墓は、墓石に「〇〇家の墓」ではなく「南無阿弥陀仏」と刻み、単なるお骨を保管場所ではなく、南無阿弥陀仏を喜び、お礼を申し上げる場所として大事にしてきました。
◆お墓をとりまく現状
少子化や価値観・家族のあり方の多様化など急速な時代の変化の中で、従来のようにお墓を親族で継承しつつ管理してくことが難しくなってきています。そして、そんな社会の変化に合わせてお墓の形も多様化してきています。
埋葬される人・単位ごとに分類するならば、これまで主流であった家単位で所有してゆく家墓(累代墓)、夫婦両家で所有する両家墓、個人で入る個人墓、その夫婦だけがはいる夫婦墓、遺骨を骨壷から出し血縁を超えてお墓に入れる合葬墓の5つに分けられます。また、お墓のスタイルで分けるならば、従来の一般墓に加え、室内で管理する納骨堂、墓石に代わって樹木を植え管理する樹木葬、自宅にお骨を安置し管理する手元供養、自然にお骨を撒く散骨などがあります。当然これらを管理している団体によって細やかな内容は異なります。このような選択肢の中から、親族がいらっしゃるなら親族でよく相談し、独居ならばご自身の死生観を通して考え、一番よい選択をすることが大切です。
◆そんな時代だからこそ
お墓の問題についてどのような選択をしようとも、お浄土へ参られたご先祖方は、南無阿弥陀仏の響きの中に身を置いて、私たちのところに届いて、私たちを支えようとしてくださっています。ある方が、お父さんのお骨の一部をペンダントにして身につけていらっしゃり「このペンダントをつけているとお父さんと一緒にいるような気がして心強い」とおっしゃっていましたが、浄土真宗の門信徒は、南無阿弥陀仏と声に出して称えれば、この南無阿弥陀仏の中に身を置いているご先祖方にいつでも会うことができます。お墓を管理してゆくことが難しくなる時代だからこそ、この口から声となってあらわれる南無阿弥陀仏の響きのなかで、ご先祖方を偲ぶ時間を大事に持ちたいものです。
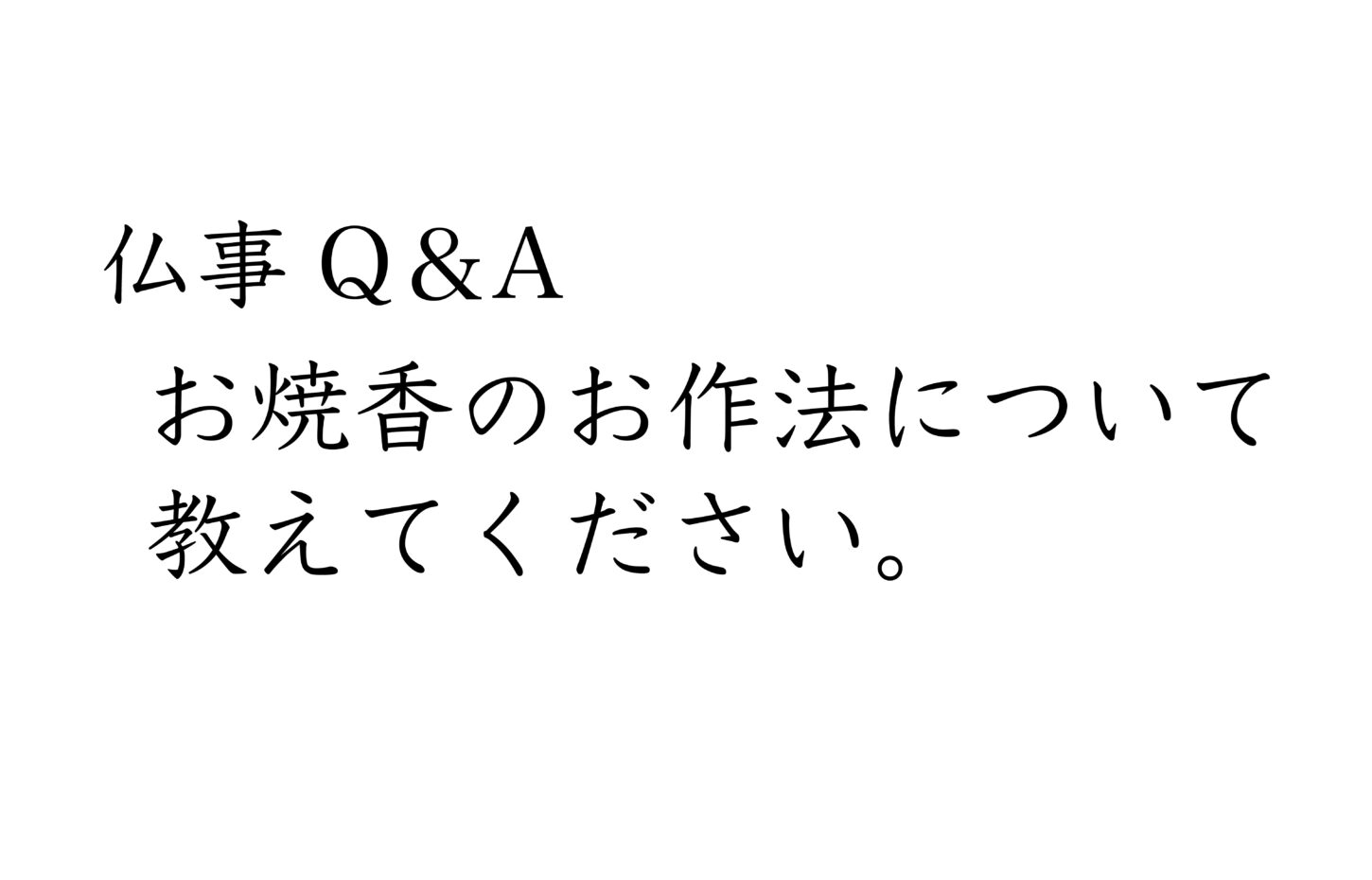
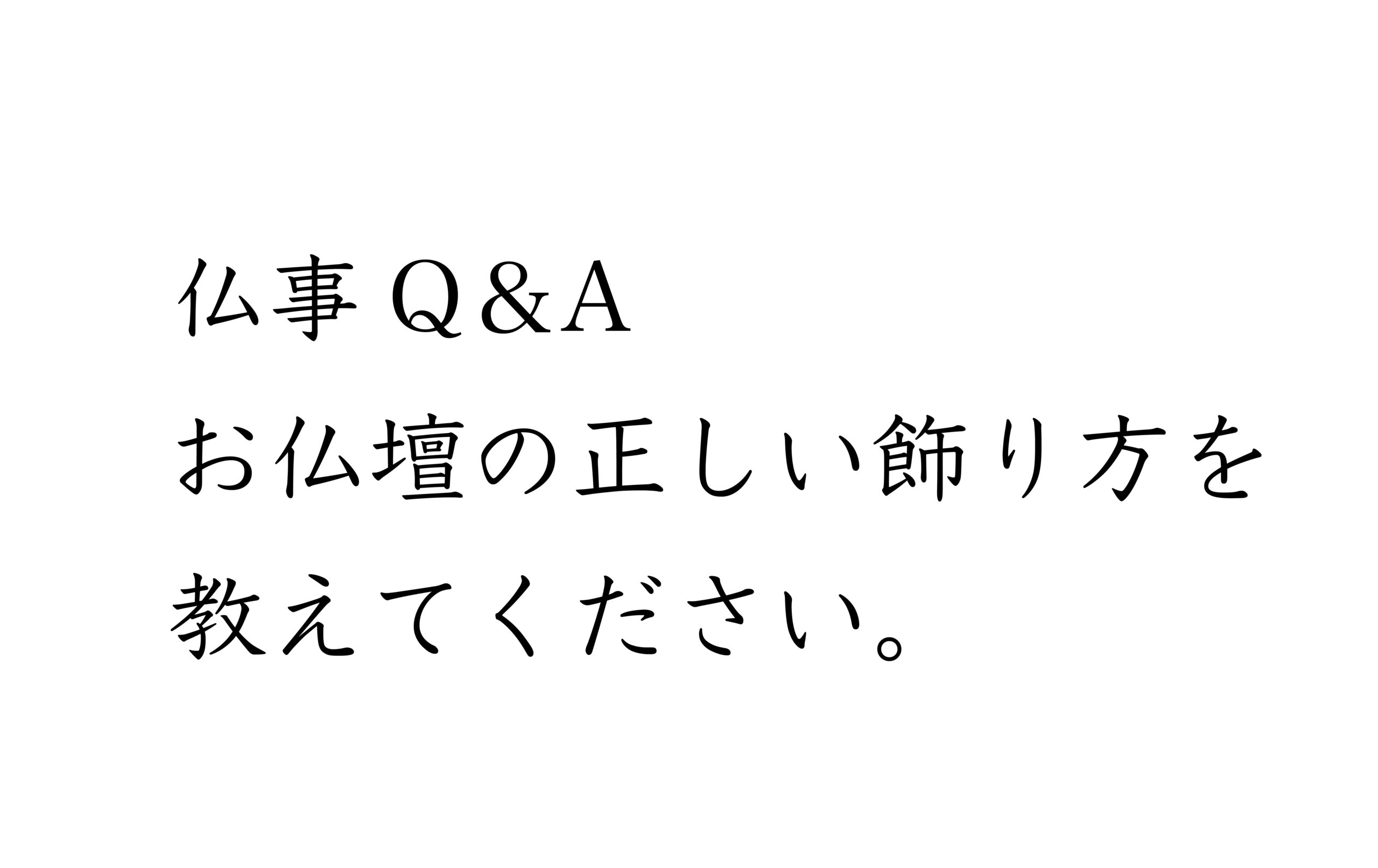
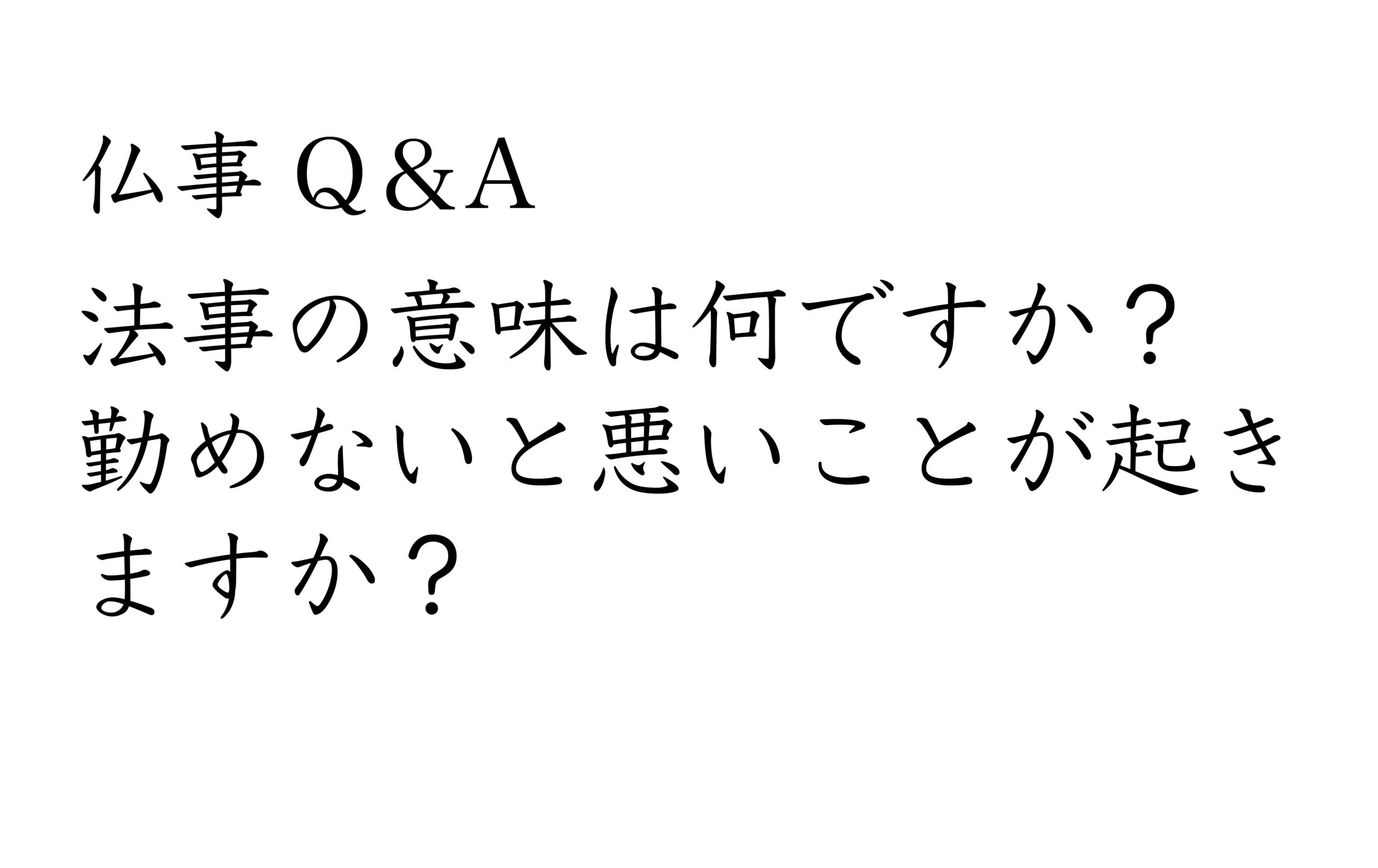

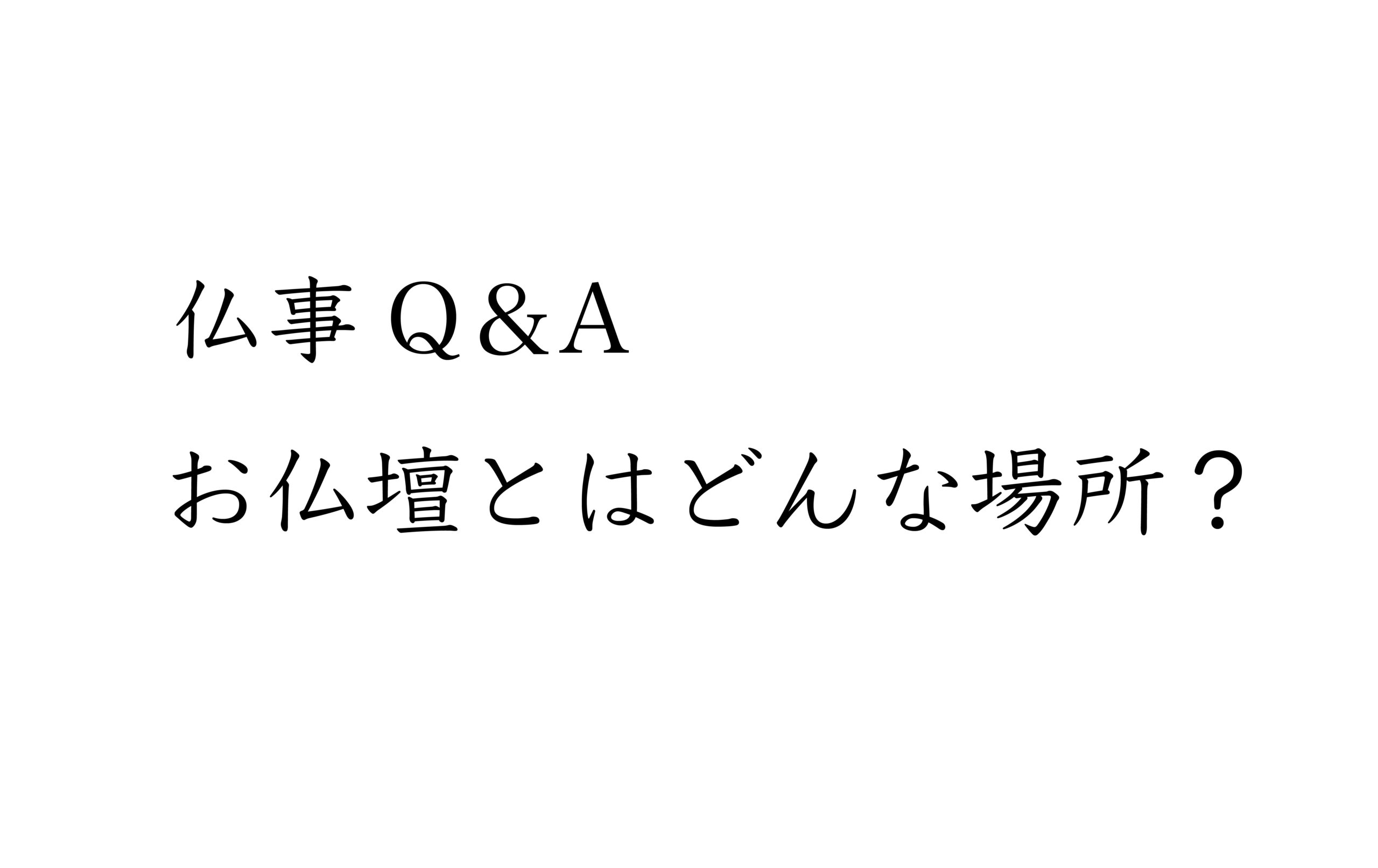

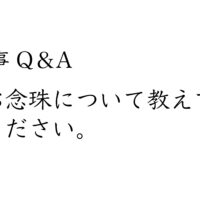
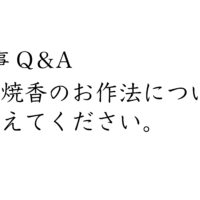

この記事へのコメントはありません。